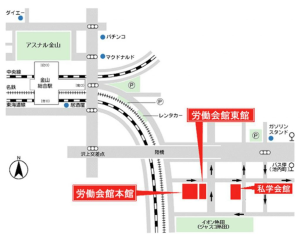●2026年度総会・第73回年会のお知らせ
2026年5月30・31日 一橋大学国立キャンパスにて開催予定
●会員情報管理方法変更のお知らせ
リンク先「2026年4月より 会員管理システムが変わります」をご確認ください。
●日本科学史学会 入会費・年会費の改定に伴う対応
2025年度の日本科学史学会総会において入会費・年会費の改訂が決定されました。次のようになります。
<入会金>
3,500円(正会員・学生会員共通)(改定前3,000円)
<年会費>
正会員 A会員10,000円 B会員15,500円(改訂前A会員9,000円 B会員14,500円)
学生会員 A会員 6,000円 B会員9,000円(変更なし)
入会費・年会費の改定に関する運用は、次のようにいたします。
・2025年およびそれ以前の会費に関しては、従来の金額(改訂前A会員9,000円 B会員14,500円)といたします。
・2025年度から会員になる入会者の入会金は3,000円とします。2026年度から会員になる入会者の入会金は3,500円となります。
・2026年度以降の会費に関して、2025年5月25日以前に前納していただいた方には、当該年度の追加請求はいたしません。
●2025年度「科学史学校」も、引き続きオンラインにて開催します。
●『科学史事典』(丸善出版)を発売中です。
 丸善出版へのリンク
丸善出版へのリンク